土木工事とは?初心者にもわかりやすく種類・内容・依頼方法を徹底解説
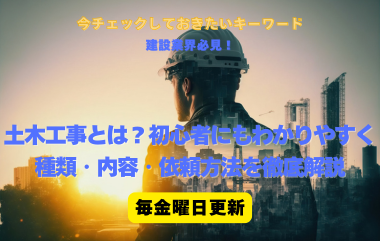
土木工事は社会におけるインフラ施設の安全性を維持する重要な工事のひとつです。しかし、具体的にどういった工事なのかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、土木工事の概要や工事の種類、事例を説明したのち、工事手順について詳しく紹介します。
目次
土木工事とは?意味と読み方をやさしく解説
土木工事とは、道路・橋・トンネル・ダムなど、生活インフラをつくるための大規模な工事全般を指し、私たちの「暮らしの土台」を整える仕事です。
まずは土木工事がどのようなものか、その概念や工事の範囲、また他工事との違いについてまとめました。
土木工事の定義と範囲
土木工事(読み方:どぼくこうじ)は、工事の根底となる法律「建設業法」において土木一式工事として定義されています。
出典:e-GOV法令検索「建設業法」
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事のことであり、ただモノをつくるだけではなく補修、改造、解体などにも対応するのが特徴です。なお土木工事の工事範囲は多岐にわたり、次のような社会インフラの整備・保全が対象となります。
- 道路(国道、県道、高速道路など)
- 橋梁(河川橋、跨道橋など)
- ダム・調整池
- トンネル
- 河川施設(堤防、護岸など)
生活基盤を支える重要なインフラであることから、主に国や自治体などから公共工事として発注されます。
また建設業法の概要を知りたい方は、こちらの記事をチェックしてみてください。
建築工事との違い
土木工事と建築工事はどちらも似た工事業務だと思われがちですが、実際には次のように「つくるもの」が違います。
以上より、建築が「建物」、土木が「インフラ」という認識が正しいと言えます。どちらも人々の生活に欠かせない仕事ですが、対応するフィールドが違うと覚えておきましょう。
なお、土木工事と建築工事の違いについては、こちらの記事でより詳しく解説しています。
とび・コンクリート工事との違い
土木工事と並列して捉えられがちなのが「とび工事」「コンクリート工事」といったキーワードです。結論として上記2つの要素は、それぞれ土木工事のなかの下層レイヤーにある要素となります。
基本的に建設業法上の専門業種として「とび・土工・コンクリート工事」と呼ばれ、登録されています。参考として以下に土木工事全般との違いをまとめました。
| 項目 | 土木工事全般 | とび・土工・コンクリート工事 |
| 工事の範囲 | インフラ全般を対象とする工事 | 特定作業に特化した工事 (掘削・足場・型枠など) |
| 専門性 | 総合的に施工管理や設計も含む | 現場の手作業を担う職人がメイン |
| 登録業種 | 総合建設業、特定建設業など | 専門工事業(28業種の1つ) |
「とび・土工・コンクリート工事」は、土木工事の現場に欠かせない「職人」に視点を当てた工事業務です。土木工事のなかにとび工事・コンクリート工事などが含まれていると覚えておきましょう。
土木工事の種類一覧|主な7つの工事を紹介
土木工事は、社会の生活基盤を支える多様なインフラを構築・維持するために実施する工事です。以下に主要な土木工事の種類とその概要を紹介します。
道路工事|舗装や拡張整備
道路工事は、人や自動車等が安全で円滑に交通できるようにする土木工事です。道路の老朽化や将来的な交通量の増加に対応し、次のような土木工事を実施します。
- 舗装工事(アスファルトやコンクリートを用いた路面の新設や補修)
- 拡張工事(車線の増設や交差点の改良による交通容量の向上)
例えば、京都府京都市の四条通では、四条通の車道を片側2車線から1車線に減少し、歩道幅員を3.5mから6.5mに拡張する歩道拡幅工事が実施されました。
出典:国土交通省「各事例解説」
歩行者の安全性と快適性の向上のために、工事がおこなわれています。
河川・治水工事|洪水対策、堤防建設
河川・治水工事は、水害から人々の生活や財産を守るために実施する土木工事です。特に近年では、たびかさなる気候変動による豪雨の増加などによって、次のような工事を実施し、適切な洪水対策が求められています。
- 堤防建設(河川の氾濫を防ぐ土手の構築や河川の掘削)
- 護岸工事(河川の浸食を防止する岸辺の補強)
例えば、九州にある筑後川水系では、城原川という河川の越水を防止するために、堤防整備が実施されました。
出典:国土交通省「治水対策の方策の主な事例」
過去の越水事例などをもとに、改修すべき場所をピックアップして土木工事を実施しています。
橋梁工事|橋をつくる技術と工程
橋梁工事は、河川や山間山間というような地形的な移動の制約を解消するために、道路と接続した橋をかける土木工事です。地域間の連携を強化するために、次のような土木工事を実施します。
- 下部工(橋脚や基礎の構築)
- 上部工(橋桁や床版の設置)
- 舗装工(上部工に道路としての役割を担う舗装を設置)
例えば、過去には愛知国道事務所で「国道302号庄内川橋」の鋼橋上部工事が実施されました。
出典:中部地方整備局「鋼橋上部工事(国道302号庄内川橋)におけるDX活用について」
特に近年では、DX化によりBIM/CIMといった要素を用いつつ、橋梁設計や工事の業務効率化が図られています。
ダム工事|水資源の確保と洪水調整
ダム工事は、降雨によって得られた水を貯蔵する目的、また洪水が発生しないように調整する目的で実施する土木工事です。安定した水供給と水害防止を担っているため、次のような形式の大規模な貯水施設を設けます。
- 重力式ダム(コンクリートの重量で水圧に耐える構造)
- アーチ式ダム(アーチ形状で水圧を両岸に分散させる構造)
なお過去の事例として、既設ダムの嵩(かさ)上げ工事なども実施されています。
出典:中部地方整備局「建設ダムにおけるDXの取り組み」
当工事においても、設計段階からBIM/CIMを活用し、コンクリート打設の自動・自律化を目指しています。
造成工事|土地を建築可能に整える工事
造成工事は、土地を建築や農業などの目的に合う状態に整備するための土木工事です。建築工事を実施する前段階として実施するケースも多く、自治体だけではなく民間企業や個人からも工事が発注されます。
- 切土・盛土(土地の高低差を調整)
- 擁壁工事(土砂崩れを防ぐための壁の設置)
なかでもよく実施されるのが土地区画整理事業です。
出典:国土交通省「市街地整備事業の事例集」
上記のように、JR代々木駅周辺の再編成では、道路の拡幅と敷地の有効利用の土木工事が実施されています。
基礎・外構工事|住宅に直結する工事
基礎・外構工事は、建物の耐久性や美観、機能性を高めるために実施する土木工事です。建築工事と連動して実施する土木工事であり、次のような作業に対応します。
- 基礎工事(建物を支える土台の構築および耐震・免振の対策)
- 外構工事(庭、フェンス、駐車場などの整備)
なお国土交通省から、外構工事やリフォームにおける制度なども登場しています。特に近年では、省エネ住宅などが推進されていることから、それに合わせて基礎・外構工事が多数実施されている状況です。
環境保全系の工事|緑地・公園・都市景観整備
環境保全系の工事は、都市や住宅地などにある緑地や公園などの自然空間を整備する土木工事です。暮らしの質と環境のバランスを保つことが目的であり、地球温暖化防止やカーボンニュートラルの実現などにも役立ちます。
- 公園整備工事(地域のニーズに合わせたレクリエーション空間を設計・施工)
- 緑地帯の造成(幹線道路沿いや河川敷に植栽スペースを確保)
- 景観整備工事(歴史的街並みや文化的景観を維持)
なかでも積極的に実施されているのが、都市公園における景観形成です。
出典:国土交通省「都市公園事業」
そのため近年では、利用しやすい公園施設等が増えてきています。
土木工事の一連の流れ
土木工事は、単に「施工」をするだけでなく、入念な計画からスタートし、設計・申請・準備・施工・検査と、いくつもの段階を経て進めていきます。参考として以下に土木工事の流れをまとめました。
- 計画・調査フェーズ
- 設計・許認可フェーズ
- 施工準備(仮設工事・安全対策など)
- 本施工(工程管理・重機使用など)
- 検査・引き渡し
段階的に実施するのは、土木工事の「安全性」「正確性」「法令順守」を徹底するためです。なかでも国や自治体が関与する公共工事では、厳格なプロセス管理が求められます。
まとめ
土木工事は「道路」「橋」「ダム」「河川」などの構造物を通じて、生活インフラを支える重要な工事です。建物を建てる建築工事とは違い、より広域かつ長期的な視点が求められます。
なお近年では建設DXとして、BIM/CIMといったプロセスが活用され始めています。自動化・効率化が進んでいる分野でもあるため、ぜひ土木工事の事例をチェックしてみてください。


