一人親方とは?やめとけと言われる真相や保険制度・年収事情まで徹底解説
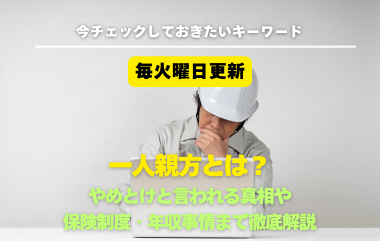
一人親方とは、企業に縛られず、自由に工事業務に従事できる働き方です。しかし、具体的にどのような仕事をする人を指すのかわからない、年収がどれくらいなのかわからないとお悩みの人もいるでしょう。
そこでこの記事では、一人親方の概要を説明したのち、辞めとけと言われる理由や年収事情についてわかりやすく解説します。
目次
一人親方とは?
一人親方とは、建設業といった分野において、労働者を雇うことなく自分一人で工事業務を請け負う事業主のことです。
職人などが会社に雇われず、ひとりで仕事を請け負う働き方であるため、会社員と比べて自由に働けます。ただし、会社に頼らず自立して働くプロフェッショナルであることから責任の大きい働き方です。
一人親方として働ける主な業種(大工・とび職など)
一人親方が活躍できる業種は、建設業に集中しています。特に現場での実務経験を持ち、自ら業務を請け負う次のような職種が該当します。
| 業種 | 内容 |
| 大工 | 木造建築の構造体・内装施工など |
| とび職 | 高所作業、足場組立など |
| 塗装業 | 壁や外装などの塗装業務 |
| 解体業 | 建物の取り壊し |
| 左官 | モルタルやコンクリ仕上げ |
| 電気工事業 | 配線や照明設置など |
工事現場で作業員と協力しながら働いているため、一見すると会社に所属しているように見える人たちばかりです。ですが実際には、会社に所属せずフリーランスとして活動するスタイルが確立しており、個々の職人が一人親方として活躍しています。
一人親方と個人事業主の違い
一人親方と似た立ち位置の働き方として「個人事業主」という言葉があります。どちらも自営業者ですが、実務の内容や制度上の扱いに次のような違いがあるとご存じでしょうか。
| 比較項目 | 一人親方 | 一般的な個人事業主 |
| 主な職種 | 建設業 (現場系が中心) | あらゆる業種 (デザイナー等も含む) |
| 労災保険の加入 | 特別加入制度あり | 原則対象外 |
| 雇用の有無 | 自身のみ (雇用なし) | 従業員を雇うケースもある |
| 所属体制 | 労働組合などに加入が一般的 | 加入義務なし |
業種の範囲が違うほか、労災保険の加入条件や労働組合への加入の必要性などが異なります。簡単なイメージとして、一人親方は個人事業主よりも関係する制度が多いのが特徴です。
一人親方に向いている人・向いていない人
一人親方は高い自由度がある分、リスクも大きいため、働き方の向き・不向きが明確です。参考として以下に、性格や業務スタイルが向いている人・向いていない人の特徴をまとめました。
【一人親方が向いている人】
- 独立志向が強く、自分で仕事を管理したい人
- 技術力があり、継続的に仕事を得られる自信・確信がある人
- 自己管理能力(体調・収支・スケジュール)に優れている人
【一人親方が向いていない人】
- 安定収入を求める人
- 営業・契約手続きなどが苦手な人
- 社会保険や税務処理に強くない人
上記の情報をもとに、一人親方がおすすめな人の特徴を下表にまとめました。
| おすすめの人の特徴 | 一人親方が合っている理由 |
| 組織に縛られず、自分のペースで働きたい | 出勤時間・上司の指示・組織のルールから解放される |
| 技術力に自信があり、独立したい | スキルを活かして直接契約・単価アップが狙える |
| 子育て・介護と仕事を両立したい | 働く時間・場所を自分で決められる柔軟な働き方が可能 |
| 収入をもっと増やしたい | やればやるだけ収入アップ、上限のない青天井スタイル |
| 自分で仕事を取り、裁量を持ちたい | 案件選びや価格交渉も自分次第で、やりがいを感じやすい |
一人親方は「自分で仕事をつくる力」が必要不可欠ですので、安定を求める人にはややハードルが高い働き方かもしれません。
一人親方になるにはどうする?
一人親方になるには、特別な資格は不要です。
ただし、税務や保険などの手続きが必要となります。特に建設業では、仕事を得るための人脈や実務経験も重要であるため、以下に一人親方になるための流れをまとめました。
- 開業届を提出する・・・税務署に「個人事業の開業届出書」を提出
- 仕事を確保する・・・元請会社や協力業者と契約(口約束でなく書面推奨)
- 仕事道具を準備する・・・工具・車両・保護具などを自前で用意
- 労災保険に特別加入する・・・労働組合等を通じて申請(厚生労働省)
ただ名乗れば良いというわけではなく、正式な手続きを踏まなければ一人親方になれません。ぜひ上記の手順を参考に、手続きをスタートしてみてください。
一人親方はやめとけ?制度廃止の噂と注意点も解説
一人親方になることに対し、一部の人たちから「やめとけ」と言われることがあります。なぜ、そう言われるのか以下に理由をまとめました。
- 収入が安定せず、生活が不安定になりがち
- 怪我や病気時のリスクを自分でカバーしなければならない
- 保険・契約関係の知識が必要でハードルが高い
なかでも「収入の不安定さ」「制度の複雑さ」が関係して始めること・続けることが難しいからやめとけと言われています。
また「一人親方制度が廃止され、企業に所属した作業員しか工事ができなくなる」といった噂が広がっていますが、それは誤解です。現時点で制度廃止の事実はないため、誰でも一人親方として働き続けられます。
一人親方になるメリット
一人親方は「自由」「収入面」という点でメリットのある働き方です。以下に、会社の縛りなく働ける魅力をまとめました。
【メリット1】自由な働き方ができる
一人親方になれば、自分で働く時間・場所・相手を選べます。会社の上下関係や出勤時間に縛られないため、ライフスタイルに合った働き方が可能です。なかでも次のような人には大きなメリットがあると言えるでしょう。
- 子育てや介護と両立しながら働きたい
- 自分のペースでスケジュールを組みたい
- 気の合う元請業者だけと仕事したい
自分の意思で働き方をコントロールしたいなら、ぜひ一人親方にチャレンジしてみてください。
【メリット2】収入に上限なく働ける
会社員と違い、一人親方は働いた分がそのまま収入になるため、やる気次第で年収を大きく伸ばせます。
企業のように役職ごとの給与の上限がなく、青天井として働けるのが魅力です。会社員よりも多くの収入を得たいと考えているなら、上限のない一人親方として働いてみるのも良いでしょう。
一人親方になるデメリット
一人親方になることには、収入の波や保険の負担といった注意点があります。甘く考えると後悔するケースもあるので、メリットと合わせてチェックしてみてください。
【デメリット1】収入が不安定になりがち
一人親方は会社員と違い、次のようなリスクの影響を受けやすいため、安定収入の保証がなく、月によって収入が大きく変動します。
- 雨続きで現場が中止→収入ゼロの月も
- ケガで休業中→生活費の不安に
- 元請との契約終了→すぐに次の仕事がないことも
特に6〜10月にかけての雨が降りやすい時期(出水期)などは、仕事できる日にバラつきが生まれるため、安定して仕事を取れるように根回しをしておくことが重要です。
【デメリット2】労災保険への加入が必要
一人親方は会社の労災に入れないため、自ら保険に加入しないと無保護状態になります。そのため、一人親方は以下の保険に加入するのが一般的です。
- 労災保険(特別加入)
- 民間の傷害保険や所得補償保険
加入した後は、継続的に保険料を支払い続ける必要があります。事故・病気が命取りになる可能性もあるので保険加入が必須だと覚えておきましょう。
一人親方の年収事情
一人親方の年収は、おおよそ日本の平均年収と同等の金額になると言われています。
例えば以下の表より、2019年時点の一人親方(全職種)の平均日額は17,138円となります。基本的に月22日(週休2日4週)働くと考えた場合には、月額約38万円をもらえる計算です。つまり年間の収入で換算すると456万円(38万円×12ヶ月)になります。
出典:厚生労働省「建設技能労働者の現状と処遇改善に向けた課題」
対して日本の平均年収は、国税庁が公開している461万円です。なお、人気の一人親方のなかには年収1,000万円プレイヤーもいます。
一人親方が加入できる保険の種類
一人親方は「労働者」ではないため、会社員向けの社会保険制度が使えません。そのため、自分で一人親方保険を選び、加入する必要があります。以下に主な保険をまとめました。
- 労災保険(特別加入)・・・労働中のケガ・病気をカバー
- 国民健康保険・国民年金・・・自営業者が加入する基礎制度
- 民間の所得補償保険・・・収入減に備える任意保険
労働組合などの窓口を通す必要があるため、労働組合への加入手続きも必要になると覚えておきましょう。
まとめ
一人親方は、建設業の仕事を自分で選べるほか、青天井で稼ぐことができる自由な働き方です。ですが一方で、保険・収入・働き方のすべてを自己管理しなければならない責任も伴います。
一人親方には一長一短な面があるため、建設工事の働き方にお悩みの方は、本記事の情報を参考にしつつ新たな働き方を検討してみてください。


