建ぺい率とは?3分で理解できる仕組みと緩和ルール【保存版】
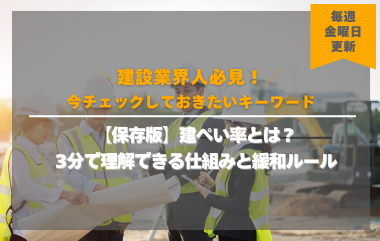
土地や住宅の購入、家づくりを始めるときに、必ずと言っていいほど登場するのが建ぺい率(けんぺいりつ)です。そしてこのキーワードのことを知らずに家を建てようとすると、後々、法律違反といったトラブルに発展するケースもあります。
そこでこの記事では、建ぺい率の概要や仕組み、計算方法を解説したのち、類似の用語である容積率との違いや、違反した場合の罰則・罰金についてわかりやすく紹介します。
目次
建ぺい率とは?
建ぺい率(読み方:けんぺいりつ)とは、都市計画や住宅建築において「どれだけの面積に建物を建ててよいか」を定めた指標です。都市計画上の建築制限のひとつであり、敷地面積に対して建物の建築面積が占める割合をパーセントで示します。
なお建ぺい率は、次のように都市計画区域の用途地域ごとに上限が定められています。
(建蔽率)
第五十三条 建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。
引用:e-GOV法令検索「建築基準法」
家づくりをする際には、一部の例外を除いて設定された建ぺい率のなかで家を建てなければなりません。
建ぺい率が定められている理由
建ぺい率の規制は、以下の理由のために導入されています。
| 目的 | 概要 |
| 都市の安全性 | 建物の密集を防いで、火災時の延焼リスクを抑制する |
| 快適な住環境 | 日照・通風の確保・生活のゆとり空間を守る |
| 美しい街並み | 無秩序な開発や過密建築を防止する |
日本の住宅の半数以上は木造であることから、建物が密な状態で建てられてしまうと、火災が起きたときに延焼リスクが高まります。また、風通しが悪くなるせいで住宅の劣化が早まるほか、無秩序で統一性のない街並みになるのがデメリットです。
対して建ぺい率を設ければ、上記のトラブルを回避しやすくなります。家を安全かつ快適なものとするために欠かせない指標だと覚えておきましょう。
建ぺい率の制限と用途地域別の基準
建ぺい率には都市計画法および建築基準法にもとづき、用途地域ごとに上限値が定められています。
その土地がどの地域区分(用途地域)に属しているかによって、建物を建てられる面積の上限が変わるため、建ぺい率の確認をする際には、以下の設定を参考にしなければなりません。
| 建ぺい率の上限 | 用途地域 |
| 50% | 第一種、第二種低層住居専用地域 |
| 60% | 第一種、第二種中高層住居専用地域、第一種、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域 、工業地域、工業専用地域 |
| 80% | 近隣商業地域、商業地域 |
例えば、住宅街として利用されている「第一種低層住宅専用地域」の場合には、建ぺい率が50%以内(後述する緩和あり)でなければ家を建てられません。家を建てる際には建ぺい率に準じなければならないと覚えておきましょう。
また建ぺい率が用途地域ごとに異なるのは、土地利用の目的・性質が違うためです。例えば、低層住宅地のように、ゆとりある環境や景観を重視するエリアは、建ぺい率を低く設定し、逆に商業地や工業地では、土地の有効活用を優先しているため建ぺい率が高く設定されています。
建ぺい率の緩和条件と特例
前述した建ぺい率の上限は、以下の緩和条件などを満たしていれば、上限値をさらに高めることも可能です。
- エリアの角地にある
- 防火地域内で耐火建築物を建築する
引用:e-GOV法令検索「建築基準法」
例えば、前項で示した建ぺい率の上限が次のように変化します。
| 用途地域 | 一般的な建ぺい率上限 | 特定条件での緩和 (角地など) |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 最大60% |
| 第二種低層住居専用地域 | 50% | 最大60% |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 最大70% |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 最大70% |
| 第一種住居地域 | 60% | 最大80% |
| 第二種住居地域 | 60% | 最大80% |
| 準住居地域 | 60% | 最大80% |
| 近隣商業地域 | 80% | 最大90% |
| 商業地域 | 80% | 最大90% |
| 準工業地域 | 60% | 最大70% |
| 工業地域 | 60% | 最大70% |
| 工業専用地域 | 60% | 最大70% |
なお上記はあくまで原則であり、実際には各市区町村の都市計画図や建築指導課にて正確な数値を確認しなければなりません。
また用途地域の情報は「自治体の都市計画図」「市区町村役所の建築指導課・都市計画課に問い合わせ」「不動産登記簿や土地調査図」などから調べられます。家を建てる際には、購入する(所有する)土地がどの用途地域に含まれているのかを確認することからスタートしましょう。
建ぺい率の計算式
建ぺい率の計算は以下の式で行います。
建ぺい率(%)=(建築面積 ÷ 敷地面積)× 100
・建築面積: 建物を真上から見た水平投影面積(㎡)
・敷地面積:建物を配置する土地面積(㎡)
例えば、敷地面積は土地の登記簿謄本から数値を把握できます。今回は150㎡としましょう。続いて建築面積は設計をする際に形づくられていく面積であり、今回は90㎡になったとします。
すると上記の計算式より、建ぺい率が60%であることがわかりました。
(90㎡ ÷ 150㎡)× 100 = 60%
つまり、建ぺい率の上限が60%までと定められているエリアでは、ギリギリ家を立てられるサイズだと判断できます。対して建築面積が広がって建ぺい率が70%になると、同じエリアでは家を建てられません。この際には、設計の段階で家の間取りを狭めて建ぺい率を抑える必要があります。
建ぺい率と容積率との違い
建ぺい率と似た指標のひとつに「容積率」という言葉があります。容積率とは、敷地に対して「どれだけの建物を建てられるか」を数値化した指標であり、建ぺい率と同じく都市計画上の制限が設けられています。以下に主な違いを整理しました。
| 項目 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 計算式 | 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100 | 延床面積 ÷ 敷地面積 × 100 |
| 規制の目的 | 空地の確保・防災・景観保護 | 過密開発の防止・住環境の維持 |
| 影響する部分 | 建物の「配置」「広がり」 | 建物の「階数」「高さ」 |
| 用途地域別制限 | 一般的に50%〜80% | 一般的に100%〜1300% |
容積率の制限がなければ、敷地面積が小さくても高層ビルのような建物が建てられてしまい、以下のような問題が起こる恐れがあります。
- 日照・通風の悪化
- 交通渋滞・騒音の悪化
- 防災面でのリスク
- 地域の景観崩壊・都市機能の不均衡
建ぺい率だけでは防ぎきれない「抜け道」の対策として用いるイメージです。家づくりでは建ぺい率・容積率の両方を確認する必要があると覚えておきましょう。
建ぺい率オーバーによる罰金・罰則リスク
建ぺい率を超えて建築した建物は、法律違反にあたるとご存じでしょうか。
たとえ数%の小さな違いでも、上限をオーバーすれば「違反建築物」となり、建築確認が下りなかったり、将来的に大きな不利益を被ったりするリスクがあります。また、次のようなリスクが起きる点に注意してください。
- 建築確認が不許可になる(工事が始められない)
- 建築後に是正勧告・除却命令(取り壊し)の対象になる
- 違反が発覚すると売却・融資・登記が困難になる
- 中古物件としての評価が著しく下がる
なお明確な罰金や罰則は設定されていませんが、建築基準法違反という枠組みで見た場合には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されるかもしれません。
建ぺい率オーバーの解決策
もし建ぺい率をオーバーしてしまった場合には、次のような対処法で早期解決が可能です。
- 建物の設計変更
- 緩和条件の適用
- 用途地域の再確認
- 建築確認前に修正
- 除却命令への対応(※最終手段)
基本的には1〜4の対策で解決が可能です。ただし、建築後に問題が発覚した場合には、最終手段として違反部分を取り壊すといった対策を講じなければなりません。
まとめ
建ぺい率は、家づくりの基本となる重要な指標です。エリアごとに定められている上限内に収めなければ、家を建てられない(建てられたとしてもトラブルに発展しやすい)点に注意しましょう。
建築士はもちろん、不動産開発業者、土地購入者など多くの人に関わる要素ですので、計算方法や上限を活用してみてください。


