建設とは?初心者でもわかる業界の仕組み・仕事内容・将来性まとめ
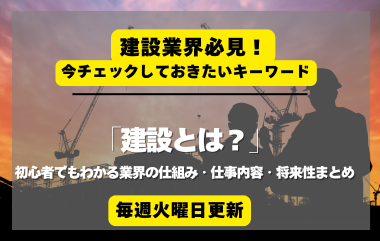
建設とは、国内の社会資本を維持する重要な役割を担う事業のひとつです。しかし、具体的に何をする仕事なのか、どのような企業がかかわっているのかイメージできない人もいるでしょう。
そこでこの記事では、建設という言葉の概念や意味を説明したのち、現在のトレンドや将来性について詳しく解説します。
目次
建設とは?意味と定義をやさしく解説
建設という言葉のなかには、住宅やビルだけでなく、道路や橋、トンネルといったインフラも含まれ、非常に幅広い分野を指します。まずは初心者でも理解できるよう「建設」の基本的な意味や定義、そして建築と土木の違いについてまとめました。
建築と土木の違い
建設業は、大きく「建築」「土木」の2つに分類され、それぞれ異なる役割を担っています。2つの違いを比較表にまとめました。
| 建築 | 土木 | |
| 目的 | 人が住む・利用するための建物をつくる | 社会インフラを整備し、地域や生活を支える |
| 対象物 | 住宅、ビル、学校、商業施設、工場など | 道路、橋、トンネル、ダム、河川、鉄道、港湾など |
| 利用者 | 個人・企業・不特定多数の人 | 地域住民・社会全体 |
| 施工場所 | 建物の敷地内 | 地域社会や公共空間 (都市・山・川・海など) |
| 設計基準 | ・建築基準法 ・消防法 ・都市計画法 | ・道路法・河川法・土木設計基準 (国交省や自治体の基準) |
| 代表的な職種 | ・建築士・施工管理技士 | ・土木施工管理技士・測量士・インフラ技術者 |
| 主な業者 | ・ゼネコン・建設会社・ハウスメーカー ・建築設計事務所・工務店 | ・土木工事業者・道路会社・インフラ専門業者・建設コンサルタント |
例えば、建築は住宅や商業施設などの建物を対象とする一方で、土木は道路、橋梁、ダムなどのインフラ整備を実施するのが主な違いです。建築と土木は対象とする構造物や目的が異なることから、建設業の中でも明確に担当する範囲が区別されます。
建設業法における建設の定義とは?
建設という言葉は、建設業を営むうえでの資質や施工品質について定められた法律「建設業法」にて、次のように定義されています。
(定義)
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
引用:e-GOV法令検索「建設業法」
例えば、住宅の新築工事を請け負うハウスメーカーや、道路工事を請け負う土木業者などは、すべて建設業法に沿って事業を実施しなければなりません。また、事業を営む際には建設業許可の取得も必要(一部例外あり)となり、法律にもとづく経営が求められます。
建設業の社会的な役割
建設業では、私たちの身の回りにある次のような「社会資本」の整備を支え、人々の生活基盤を築く役割を担っています。
- インフラ施設の整備
- 経済活動の活性化
- 安全・安心な社会の実現
- 災害時の復旧工事
- 老朽化したインフラの改修
特に建設のなかでも、土木分野において求められる役割です。対して建築分野では、国民が安心して生活できる「快適な住まい」の提供が求められます。社会の発展と人々の暮らしを支える不可欠な存在であることから、日本を支える重要な役割があると覚えておきましょう。
建設業の主な仕事内容と職種
建設業の仕事には、多種多様な職種と専門分野が存在するとご存じでしょうか。ここでは、建設現場の構造について詳しく解説します。
ゼネコンとサブコンの役割【工事業務】
建設業界では、主に「ゼネコン(総合建設業者)」「サブコン(専門工事業者)」が連携して工事を進めます。
ゼネコンとは、大規模プロジェクト全体の管理・調整を担う企業のことであり、清水建設や大成建設、大林組などが該当します。対してサブコンは、専門的な技術を提供する企業のことであり、小~中規模プロジェクトの管理のほか、ゼネコンと連携して大規模プロジェクトの一端を担うケースも多いです。
それぞれの専門性を活かし、協力して建設プロジェクトを成功に導くことから、両者は切っても切り離せない関係だと言えます。
主要な職種とその仕事内容
建設工事のプロジェクトのなかでは、次のような複数の職種の人材が従事しており、それぞれ専門的な技術を活かして工事業務を進行していきます。
- 現場監督:工事全体の進捗管理や安全管理を担当
- 施工管理技士:品質・工程・原価の管理を担当
- 鳶職:足場の組立や鉄骨の組み上げといった高所作業を専門
- 土木作業員:道路や橋梁の建設など、土木工事全般を担当
また上記のような現場関係の人材だけではなく、設計士、調査士、測量士なども建設業務に欠かせない存在です。図面の作成や現地状況の把握、土やコンクリートの状況調査などを担います。
建設業界の現状と将来性
現在の建設業界は、さまざまな社会課題と向き合いつつ、新たな技術の発展に力を注いでいます。参考として、建設業界の「現状」「これから」を、客観的なデータと共に深掘りしていきます。
高齢化・人手不足・労働環境の課題
建設業界は今、深刻な高齢化と人手不足、そして労働環境の課題に直面しています。
国土交通省の統計によると、建設業就業者の36.6%が55歳以上で、29歳以下は全体の11.6%にとどまっており、少子高齢化の影響を色濃く受けている状況です。
出典:国土交通省「令和6年版国土交通白書」
また、建設従事者が不足している影響で、次のような問題が慢性化しています。
- 若手人材の確保が難しく、現場のノウハウ継承が困難である
- 職人不足による工期遅延や品質低下のリスクが拡大している
- 建設現場の過酷さのイメージが定着し、女性や若年層の参入が限定的になる
なお働き方改革により改善しつつありますが、まだ長時間労働や3K(きつい・汚い・危険)といったイメージが人材流出に影響しています。そのため人材育成と職場環境の改善が、今後の建設業界の持続可能性に直結する最重要課題だと言えるでしょう。
建設×テクノロジーの進化
建設DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進により、近年の建設業界では、次のような先端テクノロジーの導入が急速に進んでいます。
- BIM:3Dモデルで設計・施工を一元管理してミスを削減できる
- ドローン測量(UAV測量):広大な現場の測量を短時間・高精度で実施できる
- ICT建機・建設ロボット:土工・鉄筋組立・塗装などを自動化して作業者の負担を軽減できる
- 遠隔監視システム:現場の安全管理をIoTで可視化できる
労働力不足を補完できるだけではなく、生産性向上や安全性確保に大きく貢献します。以前まで遅れ気味だった建設業界のテクノロジーですが、すでに他業界よりも先に進み、「肉体労働中心」から「知的生産型産業」へ進化しつつある状況です。
建設業の需要と展望
人手不足に悩まされている建設業界ですが、今後も「なくならない仕事」として安定した需要が見込まれます。以下になくならない理由をまとめました。
- インフラ老朽化対策
- 再開発・都市整備
- 災害復旧・防災インフラ
まず建設工事には、以下のように7兆円近い予算が組まれています。昨年度よりも予算額が増額されていることから、国土強靭化のために今後も安定した経営を望めると期待されます。
出典:国土交通省「令和7年度 予算概算要求概要」
社会のインフラを支える仕事であるため、景気変動に左右されにくく、長期的に安定性のある事業を継続できるでしょう。
建設業に関するよくある疑問
建設に関するよくある質問をまとめました。
建設業はキツイって本当?
建設業はよく「体力的にキツイ」というイメージをもたれやすいですが、それは一部の作業に限られます。近年の現場作業は重機・ロボットに代替されつつあり、施工管理や設計、企画などデスクワーク型の職種も増えていることから「建設=肉体労働」という時代は変わり、多様な働き方が可能です。
建設は未経験でも働ける?
建設業は、未経験からチャレンジできます。多くの企業が入社後の研修やOJTを通じてスキルを身につける仕組みを整えており、国家資格の支援制度(資格手当や受験費用の補助など)を整備した企業が増えています。
建設は女性も活躍できる?
建設業では現在、女性の進出が急増しています。例えば、国土交通省は平成26年から「もっと女性が活躍できる建設業行動計画」を推進しており、現場環境の改善や設備の整備が進行中です。女性用トイレ・更衣室の整備、時短勤務制度なども導入されつつあります。
まとめ
少子高齢化の影響を強く受けている建設業ですが、今後も持続的かつ安定した経営を続けられる環境が整っています。また近年では、建設DXの推進により、建設業界全体の効率化が進んでいる状況です。
未経験からチャレンジしやすく、日本の国土整備の一端を担う重要な仕事に従事できることから、技術分野での新たな挑戦を探している人に最適な業界だと言えます。


