技能実習制度と育成就労制度の違いとは?既存制度の廃止理由や問題点をわかりやすく解説
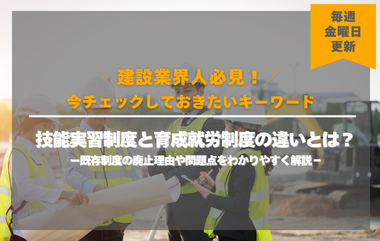
人手不足が加速する建設業の課題を解決するため、近年では外国人労働者を取り込もうとする施策が講じられています。そういったなか2024年6月14日より、技能実習制度が廃止され、新たに育成就労制度が閣議決定されました。
そこでこの記事では、技能実習制度と育成就労制度の違いをわかりやすく解説したのち、制度のメリットや問題点について紹介します。
目次
技能実習制度とは
技能実習制度とは、1993年よりスタートした外国人労働者を国内に受け入れる制度です。
最長5年間の受け入れを条件として、建設企業の従事者がOJTを実施しつつ技能実習生を教育し、その代わりに国内の工事(建設業の場合)に寄与してもらう狙いで制度が設けられました(なお、目的はあくまで技能実習生の育成がメイン)。参考として以下に、技能実習生を受け入れるまでの流れを掲載します。
- 受け入れ計画を立てる
- 技能実習生送り出し機関へ求人を依頼する
- 技能実習計画を作成して外国人技能実習機構で認定申請を受ける
- 認定通知書が交付されたのち法務省に在留資格認定証明書交付申請をおこなう
- 日本大使館等でビザ申請をおこなう
- 航空券を購入後、技能実習生が1ヶ月間の入国後講習を受けたのちに配属される
全体のプロセスは、約4〜5ヶ月程度の期間が必要です。なお、初めての受け入れではさらに技能実習計画の認定審査を受けなければならず、プラス1ヶ月が必要になります。
また技能実習生の受け入れは、非営利団体から人材を受け入れる「団体監理型(約9割が選択)」、海外現地法人等から人材を受け入れる「企業単独型(約1割が選択)」の2つから選べます。一度に受け入れられる実習生の人数にも上限があり、技能実習生の在留資格が何号なのかによって上限が変化する点に注意が必要です。
技能実習制度は2027年までに育成就労制度へと移行します
1993年より続いている技能実習制度ですが、2024年6月14日に制度廃止および「育成就労制度」への移行に関する法令改正が国会で可決・成立されました。
技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、就労を通じた人材育成及び人材確保を目的とする新たな在留資格として育成就労の在留資格を創設し、育成就労計画の認定及び監理支援を行おうとする者の許可の制度並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設けるほか、1号特定技能外国人支援に係る委託の制限、永住許可の要件の明確化等の措置を講ずる。
引用:法務省「改正法の概要(育成就労制度の創設等)」
ちなみに育成就労制度は、技能実習制度と同じく外国人雇用のための制度です。技能実習制度に対する制度目的と実態とのかい離や外国人の権利保護などの課題が指摘されていたことから、外国人にとって魅力ある制度を構築することを目的とし、制度の中身が改正されることに伴い、制度の名称が変更されました。
なお、技能実習制度はおおむね2027年(改正法の公布日である令和6年6月21日から起算して3年以内)までは継続する予定ですが、その後は新たに設けられた「育成就労制度」へと完全移行します。就労者の受け入れ内容が部分的に変更されているため、後述する2つの制度の違いをチェックしてみてください。
技能実習制度と育成就労制度の違い
出典:公益財団法人国際人材育成機構『「技能実習制度」が「育成就労制度」に変わります
技能実習制度と育成就労制度の違いを下表にまとめました。
| 技能実習制度 | 育成就労制度 | |
| 目的 | 日本での技能等の修得等を通じて人材育成をし、国際貢献をおこなうこと | 日本の人手不足分野における人材育成と人材確保をおこなうこと |
| 在留期間 | 原則1~2年特定技能取得で5年~ | 原則3年 特定技能取得で5年~ |
| 転籍 | 原則不可 | 可能 |
| 在留資格 | 技能実習1号(1年)技能実習2号(2年)技能実習3号(2年) | 育成就労(3年) |
外国人労働者が、以前の制度よりも自由に働く先を選べるようになったというのが全体的なイメージです。
なお技能実習制度の際に設けられていた「在留資格技能実習1・2・3号」の在留資格は廃止され「育成就労」という項目にまとめられました。外国人労働者は以前よりも、長く日本に滞在できるほか、待遇が悪い就労先がある場合には転籍ができるようになりました。
技能実習制度から育成就労制度に移行するメリット
以下に、技能実習制度から育成就労制度に移行する建設企業側のメリットをまとめました。
日本語能力に優れる人材を受け入れやすい
育成就労制度には日本語能力の条件が定められていることから、技能実習制度の頃よりも日本語能力に優れた人材を受け入れやすくなるのがメリットです。
例えば、今までの技能実習制度では日本語能力に関する明確な基準が定められていなかったため、なかには日本語を話せない外国人労働者も多く、コミュニケーションの面でトラブルが起きていました。
対して育成就労制度には、日本語能力N5以上という条件が設定されています。
出典:日本語能力試験「N1~N5:認定の目安」
以上より、日本語を理解した状態から建設工事に受け入れることができ、コミュニケーションに関するトラブルを回避しやすくなったのがメリットです。
短くとも3年間の長期滞在ができるようになった
技能実習制度から育成就労制度に変わることにより、以前よりも長く人材を長期雇用できるようになりました。
まず技能実習制度の場合、在留資格技能実習1号なら1年、2・3号なら2年であることから、在留期間を延ばせる特定技能の在留資格を取得しづらい状況でした。一方で育成就労制度は3年間という長い猶予があるため、特定技能を取得しやすいのが魅力です。
以上より、以前の制度よりも特定技能の在留資格へつなげていきやすくなり、外国人労働者を確保しやすくなったと言えるでしょう。
技能実習制度から育成就労制度へ移行する問題点
技能実習制度から育成就労制度へ移行することには、主に2つの問題点があると言われています。何が課題に挙がっているのか詳しいポイントを見ていきましょう。
企業の費用負担が増える
技能実習制度から育成就労制度に変わることにより、今後1人あたり年間50〜100万円の費用増加があるかもしれないと言われています。参考として、育成就労制度にかかる費用を以下に整理しました。
- 渡航関連の費用(宿泊費や航空券代など)
- 送り出し機関に支払う費用(研修費や手数料など)
- 教育支援費用(教材費や日本語教育費)
なお、来日費用については企業側が5割以上負担するという指針であることから、費用負担が大きくなりやすい点に注意が必要です。
人材流出リスクが増大する
転籍が可能である育成就労制度は、外国人労働者が働くための選択肢を増やせる便利なルールですが、企業側としては人材流出のリスクが高い点が問題視されています。
例えば、長期雇用を見越して育成をしていたものの、技能検定に合格後、すぐ別の会社へ転籍されるかもしれません。企業がかける費用に対する効果を得られない恐れもあることから、体力的に忙しい建設業では、人材流出の影響を受けやすいと予想されています。
まとめ
技能実習制度はすでに廃止が決定しており、おおむね2027年あたりに育成就労制度へと移行する予定です。
また企業にとって在留期間を延ばしやすい、日本語コミュニケーションを取りやすいといったメリットがある一方で、企業負担増や人材流出のリスクがある点が課題に挙げられています。制度のスタートでどのように進展していくのか、今後の動向から目が離せません。


